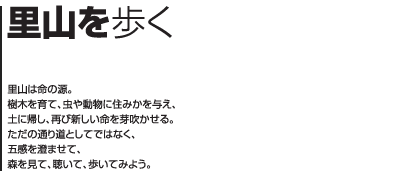|
 |
 |
ヤマユリ
夏に白い大輪の花を咲かせ、秋においしいユリ根をふとらせる。
|
|
オオイワカガミ
葉の表面の鏡のような光沢からこの名がついた。春に淡いピンクの花を咲かせる多年草。
|
|
ウリハダカエデ
樹皮をはぐとウリのような香り。枝は12月23日のダイシコウのはしやつえにした。
|
|
カラムシ
イラクサ科の宿根草。強じんで美しい繊維は越後縮やアンギンの材料になった。
|
|
ミズキ
小正月に豊作を祈り、枝に団子を刺して団子飾りにした。
|
|
ヤマグワ
葉は蚕の飼料として栽培。熟した紫色のクワの実は子どものおやつに。
|
|
コシノカンアオイ
林の中に生える多年草。ハート型の葉は春の女神ギフチョウの食草。
|
|
タニウツギ
方言名はカジバナ。2cmほどに切って山鳥の羽を刺し、小正月のハネッケエーシの羽根に。
|
|
ヒツジグサ
日本の睡蓮。十日町市内の古い沼池に生育し、白い花を咲かせる。
|
|
ブナ
市の木。冷温帯の森を代表する落葉高木。実はおやつ、木はコシキなどに加工。まきや炭用に最適。
|
|
ヤマモミジ
紅葉が美しい。小白倉の秋祭り「もみじ引き」で村中をひっぱる。
|
|
ヤマフジ
方言名はクズ。農作業に欠かせない箕(み)のすくい口にフジヅルを織り込んだ。
|
|
ホオノキ
葉は長さ40cm、幅25cmにもなり、昔はホイル代わりに使われた。木の幹はイザリ機の杼(ひ)や苧桶(おぼけ)にした。
|
|
ミズナラ
秋に美しく紅葉する。縄文人は実をアク抜きにして食用に。
|
|