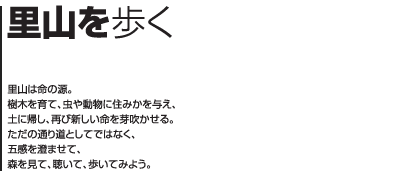|
 |
 |
|
|


|
 |
 |
ポイント1 |
 |
 |
 |
 |
トンボの主役交代!?
年を越す「越年トンボ」登場!!
目指すはキョロロの裏山にあるため池。途中、水辺で羽を乾かすオオルリボシヤンマを発見! 威風堂々とした美しい姿に歓声が上がる。7月ころから姿を見せ始めるが、よく見かけるのは9月から10月。ギンヤンマがいる間は追い払われるらしい。ところで、トンボは1年中いるって知ってる? 松之山には雪の中もスイスイと、冬を元気に越すトンボがいる。その名も「越年トンボ」。驚くほど細い小柄なトンボだ。
|
 |
オオルリボシヤンマ
狩りの得意な水辺の名ハンター!
水草の生える大きな池を好む。
|
|
オツネントンボ
年を越えると書く「越年トンボ」。
その名の通り冬になると顔を出す。
|
|
 |
|
 |
 出発!! 出発!!
|
 |
 |
ポイント2 |
 |
 |
 |
ため池で春を待つ生き物たち
いよいよため池に到着。「水の生き物はすばしこいから、網を入れて、サッとすばやくさらうのがコツだぞ〜」と博士。網を入れてはのぞきこむ子どもたち。いた、いた!ドジョウとヤゴ(トンボの幼虫)を発見。ヤゴはため池で冬を越し、5月に成虫になるクロスジギンヤンマの子どもたち。成虫になるまでに約200匹もおたまじゃくしを食べる水辺のギャングだ。
|
 |
|
 |
|
 |
 なにがかかったかな? なにがかかったかな?
|
 |
 |
ポイント3 |
 |
 |
 |
まわりの環境から生き物の習性が見えてくる
網を入れること10分。網の中で飛び跳ねる茶色の生き物を発見。水草をほどいてみるとヤマアカガエルだ。博士によると、このカエルは春の産卵から秋まで水辺で過ごし、晩秋になると森に入って冬眠するという。水辺と森がセットになった地域でしか生きられないカエルなのだ。松之山の里山はその条件にぴったりの環境だという。
|
 |
|
 |
|
 |
 なんかハネてるよ! なんかハネてるよ!
どれどれ…
|
 |
 |
ポイント4 |
ついに絶滅危惧種
オオゲンゴロウを発見!!
みんなの憧れの的「オオゲンゴロウ」はなかなか見つからない。元気を出し、池を替えてねばること20分。網の中をすばやく動く大きな虫を発見。みんなの胸が期待にふくらむ。カーキブラウンの背中に黄色のフチドリは間違いなく「オオゲンゴロウ」だ。「やったー!!」昔はたくさんいたオオゲンゴロウも今ではすっかり絶滅危惧種。東京と神奈川ではもう見つからない。
|
 |
 ついにオオゲンゴロウを発見! ついにオオゲンゴロウを発見!
|
 |
 |
ポイント5 |
最後まで飼うこと
それが虫取りのルール
今日捕れた生き物を種類ごとに分ける。「家へ持ち帰る場合は最後まで飼うか、標本にするんだぞー!」と博士。決して「池に戻さなきゃダメ」とは言わない。なぜ? の問いに「虫を捕って観察した経験が、命について考えるきっかけになるから」と答えてくれた。自分の手で捕り、よ〜く観察し、最後まで責任を持つ。そこで得られた発見が身近な環境に目を向ける大きなきっかけになる。
|
 |

|