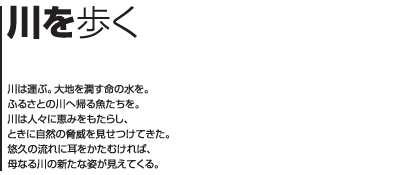交通路として栄えた信濃川、
もう一つの文化
鉄道や車が今のように普及する以前、信濃川の渡し船は、流域に住む人々の交通の足として、また、米や燃料を運ぶための重要な運送手段として活躍していた。信濃川流域には津南から寺泊にかけて約30もの渡し場があり、船頭は毎日対岸のまちや中州の畑へと人々を送った。大河をわたる信濃川船頭のみごとなかじさばきは、ほかの川の船頭さんにも絶賛されたという。山に生きる人々が田を耕し、家畜を育てて暮らしていたように、川には川の暮らし方があり、独自の文化が育っていった。
【インタビュー】
人や米を船で運び、魚や薪をとる。
信濃川は生活そのものだった。
かつて川漁師をしていた田中昭二さんは、代々川西の孫左エ門の渡しを務める家に生まれた。川が大好きだった田中さんは物心つくころから父親について川に入り、魚の捕り方や渡し船の操り方を見よう見まねで覚えていったという。「紅連舫という大きな舟でな、人を川向こうや中州に送ったり、長岡の長生橋まで米を運んだりしたもんだ。川では夏はアユ、秋から冬はサケ、2月は寒マス(サクラマス)が捕れる。この寒マスがなかなか捕れなくてな。売れれば1本1万円の高級品だ。上等の料亭で売れると本当にうれしかった」。人や米を運び、川で捕れた魚を売って生計を立てる。川は収入源であり生活の場そのものだった。燃料の薪も川から調達したという。「川で暮らすもんは流木を薪にするんだ。大雨が降って川が増水すると上流から木がどんどん流れてくる。その木を引き上げるのが命がけでな。引っかける場所をまちがうと、流れる木に引きずられて自分が川に落ちてしまうんだ。川にはルールがあってな、引き上げた流木には印をつけておく。そうすると他人は絶対に手をつけないんだ」。山には山の、川には川の暮らしとルールがある。かつて満々と水をたたえ、交通路として栄えた信濃川のもうひとつの文化がここにある。
|
 |
 筒(つづ)という網には、鯉やフナがかかる。 筒(つづ)という網には、鯉やフナがかかる。
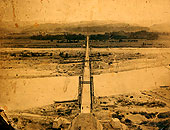 大正13年の十日町橋。川の真ん中には大きな中州が広がっていた。 大正13年の十日町橋。川の真ん中には大きな中州が広がっていた。
|