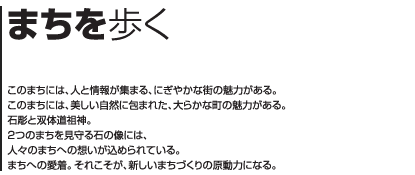|
 |
災厄の侵入から集落を守る、道の神様
涼しい風の中に、ときおりふっと濃い緑のにおいが漂ってくる。空を見上げると、そこには樹齢250年の大きな杉。皮をよじらせ天へ天へと大きく枝を広げている。ここは中里の角間。杉の大木は集落の人々の敬意を集める「ねじり杉」。その根元では一対の男女の石像、双体道祖神が手をとりあい、優しくほほえんでいた。
かつて道祖神は、塞の神や道の神ともいわれ、集落や旅人を疫病や魔ものから守り、家庭円満をもたらす神として人々の信仰を集めてきた。今ほど暮らしも安定せず、旅も危険と隣合わせだった時代。まちの人々や通行人は、集落の境目や分かれ道に立つ道祖神に手を合わせ、安全を願ったという。
1月15日に行われる松焼き(どんど焼き、ドウラクジン)は、道祖神信仰を今に伝える小正月行事。ドウラクジンは道祖神が語源だ。正月のシメ縄や門松を集めて燃やし、ハナミズキの木の枝につけた団子をその火であぶって食べると体が丈夫になると信仰されている。木や稲ワラで作った男女の人形などをご神体として、その年の五穀豊穣や家内安全、厄除けを祈願するもので、地域色ゆたかなさまざまな風習が伝わっている。
道祖神のご神体には、木や稲ワラの人形のほか、自然石や丸石、陰陽石などがあるが、双体道祖神とは一つの石に男女を彫った石像。中部地方を中心に多くみられ、中里には約19体の双体道祖神が残っている。双体道祖神の慈愛に満ちた表情は美しく、それぞれに少しずつ異なる表情を見て歩くのもおすすめ。
むかしは集落の境目にあった道祖神も、車が走り、道路が舗装されるたびに場所を移され、元の位置を知ることは難しくなってきた。道が変わり、まちが変わり、家も人もどんどん変わっていく。しかし、どんなに時代が変わっても、平和な暮らしを願う人々の想いは変わらない。数百年の時を超えて、双体道祖神は今日も静かに人々の暮らしを見守っている。
|
 |
清田山 山田正一宅入口
この双体道祖神はむかしからこの場所にあるという。砂利道がアスファルトになり、人々の服が和服から洋服へと変わっても、ずっとこの場所で往来を見守っている。
|
|
 |
 干溝薬師様脇 干溝薬師様脇
 角間ねじり杉脇 角間ねじり杉脇
|