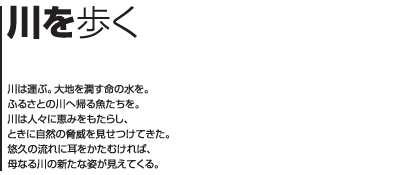原から緑の水田へ
一本の水路が開いた中里の未来
信濃川の支流、清津川の右岸に広がる桔梗ヶ原。秋になると黄金色の穂を実らせるこの土地は、今から300年ほど前までは、少しだけ田畑がある寂しい土地だった。段が高いために水を引くことができなかったからだ。度重なる日照りで極限の生活に追い込まれた人々は1785年(天明5年)、用水路を作り、桔梗ヶ原に新しい水田を作ることを決意する。約2年後、全長9キロに及ぶ長い水路が完成する。それから約220年余り。江戸時代に開かれた用水路は、それぞれの時代で改良や修復を重ね、今もこの地に清津川の水を届けている。
【インタビュー】
いまこうして農業ができるのも
先人たちの苦労のおかげです
「むかしの人々のおかげです」。通り山で農業を営む小巻澤春雄さんは、川面から一段高い段丘を指さした。「あの段丘の中には江戸時代に作った水のトンネルが通っていてね。この水路ができたおかげでこの地域一帯に水が引けるようになったんです。まとめ役となったのが庄屋の村山五郎兵衛という人物。この人がいなかったら、この水路は実現しなかったでしょう。1969年にトンネルを改修し、ポンプが取り付けられて、さらに上の段丘まで水が上がるようになりました」。こうして原といわれた中里の段丘は水を得て、徐々に緑の水田へと変わっていった。
|
 |
 通り山 小巻澤春雄(はるたか)さん 通り山 小巻澤春雄(はるたか)さん
|