自転車の交通安全
自転車の「ながらスマホ」、「酒気帯び運転」は罰則対象です
令和6年11月1日に「改正道路交通法」が施行され、自転車運転中にスマートフォン等を使用する「ながら運転」(「ながらスマホ」)の罰則が強化されました。また、「自転車の酒気帯び運転」が新たに罰則の対象になりました。
自転車運転中の「ながらスマホ」に対する罰則
【禁止事項】
・自転車運転中にスマホで通話すること。(ハンズフリー装置を併用する場合等を除く。)
・自転車運転中にスマホに表示された画面を注視すること。(どちらも自転車が停止しているときを除く。)
【令和6年11月からの罰則内容】
・自転車運転中に「ながらスマホ」をした場合は、6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金
・自転車運転中の「ながらスマホ」により交通事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
自転車の「酒気帯び運転」「ほう助」に対する罰則
これまでは酩酊状態で自転車を運転する「酒酔い運転」のみ処罰の対象でしたが、令和6年11月の改正道路交通法の施行により「酒気帯び運転」も罰則の対象となります。また、自転車の飲酒運転をするおそれがある人に酒類を提供したり、自転車を提供したりすること(酒気帯び運転のほう助)も禁止です。
【禁止事項】
・酒気を帯びて自転車を運転すること。
・自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供すること。
・自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供すること。
・自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗すること。
【令和6年11月からの自転車の酒気帯び運転に関する罰則内容】
・酒気帯び運転は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合は、自転車の提供者に3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合は、 酒類の提供者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
・自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗し、自転車の運転者が酒気帯び運転をした場合は、 同乗者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
(注意)アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自転車を運転する行為は「酒酔い運転」とされ、今般の改正道路交通法施行以前から罰則として5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が規定されています。
自転車の「ながらスマホ」が罰則強化!「酒気帯び運転」は新たに罰則対象に!(政府広報オンラインホームページ)
ヘルメットの着用
ヘルメットの着用が努力義務化されました
令和5年4月1日から全ての自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されました。
ヘルメット非着用で自転車事故により亡くなった人の約6割が頭部を損傷しています。また、ヘルメット非着用時の致死率は、着用時と比べて約2.2倍も高くなっています。(平成29年~令和3年合計。警察庁資料より)
自分自身の命を守るため、自転車に乗るときはヘルメットを必ず着用しましょう。
自転車ヘルメット着用啓発チラシ(新潟県・新潟県警察作成) (PDFファイル: 2.0MB)
ヘルメットを着用された方のことばをお聞きください
新潟県警察では、自転車乗車用ヘルメットの着用促進を図るため、ヘルメットを着用している人の声を集めたメッセージ動画「自転車に乗るあなたに伝えたいことがあります~自転車ヘルメット着用促進メッセージ~」を作成し、YouTubeにて公開しています。
新潟県警察公式チャンネルにて配信をしています。下記外部サイトよりご覧ください。
自転車に乗るあなたに伝えたいことがあります~自転車へルメット着用促進メッセージ~(新潟県警公式チャンネル)
自転車安全利用五則(令和4年11月1日交通対策本部決定より)
1 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
自転車は、道路交通法上「軽車両」に位置づけられるため、歩道と車道の区別があるところでは「車道通行」が原則です。
また、車道を通行する場合は、左側に寄って通行しましょう。
歩道を通行できる場合は、車道寄りの部分をすぐに停止できる速度で通行し、歩行者の通行を妨げるときは一時停止をお願いします。
2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
信号機のある交差点では、信号に従って安全を確認し通行しましょう。
道路標識等により、一時停止すべきとされている場所では、必ず一時停止し安全を確認しましょう。
3 夜間はライトを点灯
夜間は、前照灯及び尾灯(又は反射器材)をつけましょう。
前方を照らすだけでなく、自分の存在を相手に知ってもらうためにも重要です。
4 飲酒運転は禁止
お酒を飲んだときは自転車に乗ってはいけません。
5 ヘルメットを着用
自転車に乗るすべての人は乗車用ヘルメットを着用しましょう。
幼児・児童を保護する責任のある人は、幼児・児童を自転車に載せるときは、乗車用ヘルメットを着用させるようにしましょう。
「自転車安全利用五則」チラシ(内閣府作成) (PDFファイル: 926.1KB)
自転車の安全利用におけるリーフレットについて
自転車も車と同じ車両です。交通ルールをきちんと守りましょう。
内閣府、新潟県では「自転車の安全運転」についてチラシを作成しています。下記ファイルをご確認ください。
自転車安全利用啓発リーフレット(内閣府作成) (PDFファイル: 1.9MB)
高校生活を楽しむには自転車の安全運転から (PDFファイル: 3.0MB)
万一の事故に備えて自転車保険に加入しましょう
新潟県では「新潟県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」により、令和4年10月1日から自転車利用者の保険加入が義務化されました。
自転車事故に係る高額賠償請求事例も発生しているため、万一に備えて自転車保険に加入しましょう。
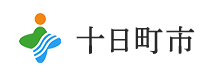
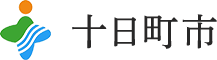
更新日:2025年03月03日