十日町市下水処理センターの下水処理の仕組みについて
十日町市下水処理センターにおける下水処理の仕組みについて説明します。
(センターの概要については、以下のリンクをご覧ください)
十日町市下水処理センターでの下水処理について
第1工程:沈砂池
汚水と一緒に流れ込む大きなごみを取り除きます。
第2工程:ポンプ室
沈砂池で、砂やごみを取り除いた汚水をポンプでくみ上げて最初沈殿地に送ります。
第3工程:最初沈殿池(初沈)
沈砂池では取り除くことのできない小さなごみを取り除きます。
第4工程:エアレーションタンク
水処理施設の心臓部とも言えるところです。最初沈殿池より送られてきた汚水に活性汚泥(好気性微生物を多く含んだ泥)を加え、空気を吹き込んで攪拌します。この間に微生物は水中の汚物を食べて繁殖、増殖します。
好気性微生物とは、動物と同じく酸素を必要とする微生物のことです。1立方センチメートル(角砂糖1個くらいの大きさ)の中に約1万匹います。
第5工程:最終沈殿池(終沈)
エアレーションタンクで処理された水は、この池をゆっくり流れる間に活性汚泥が底に沈み、きれいに澄んだ水になります。その中でも最上層の最も透明な水が塩素混和池へと運ばれます。
底に沈んだ活性汚泥は、そのほとんどをエアレーションタンクの口元に返してやり、再び汚物を食べる仕事をさせます。これを返送汚泥と言います。しかし、活性汚泥は常に増殖しているので、余分なものが部分が出てきます。その分は汚泥処理に回すのですが、これを余剰汚泥と呼びます。
第6工程:塩素混和池(滅菌池)
最終沈殿池から送られてきた上澄み水には、まだ大腸菌等のばい菌が多く含まれているので、この池で塩素(十日町市では次亜塩素酸ナトリウム溶液)を入れて消毒して川に放流しています。
十日町市下水処理センターのその他の処理施設について
汚泥濃縮槽
最終沈殿池から出てきた余剰汚泥は、その約99.5%が水の状態です。汚泥処理をするには量が多いので、ここで水分と汚泥分にわけて濃縮し、汚泥の濃度を高めて処理をしやすくします。
汚泥消化タンク(消化槽)
汚泥濃縮槽で濃度を高めた汚泥をこのタンクに入れて、嫌気性微生物(酸素を必要としない微生物)の働きにより、時間をかけて有機分を分解させます。(簡単に言うと腐らせる)十日町市では40日位かけています。
〈一次消化タンク〉 汚泥と嫌気性微生物を混ぜて汚泥を発酵させます。
〈二次消化タンク〉 汚泥を水と分離させ、汚泥を安定化させます。
汚泥脱水設備
消化された汚泥はここで脱水処理されます。この脱水された汚泥(脱水ケーキ)は委託処分先までダンプで搬送され、セメント原材料や堆肥として再利用されています。
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道局 上下水道課 下水道係
所在地:〒948-0072 新潟県十日町市西本町三丁目688番地(十日町市下水処理センター内)
直通電話番号:025-757-3141
ファックス番号:025-752-7009
メールでのお問い合わせはこちら
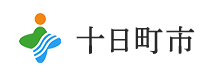
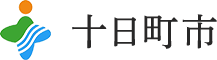
更新日:2021年04月01日