介護サービスを利用するとき
介護サービスを利用するには、申請をして要介護(要支援)認定を受ける必要があります。
要介護(要支援)認定申請ができる方
- 介護や支援を必要としている65歳以上の方
- 医療保険に加入している40歳~64歳の方で、特定疾病※により介護や支援が必要となる方
詳しくは、※特定疾病の選定基準の考え方(厚生労働省)をご覧ください。
申請に必要なもの
- 介護保険被保険者証
- 要介護認定・要支援認定申請書
- 主治医意見書問診票
申請書及び問診票の様式は、「介護保険に関する申請書」をご覧ください。
※40歳~64歳の方は、「40歳~64歳の方向け(PDFファイル:209.1KB)」をご覧ください。
申請から認定を受けるまで
1 相談・申請
- 市窓口(市役所介護保険9番窓口または各支所地域振興課市民係)や地域包括支援センターなどにご相談ください。
- 申請は、申請者ご本人またはご家族のほか、地域包括支援センターなどに代行してもらうこともできます。
- 市窓口に申請書類を提出してください。
2 認定調査・主治医意見書
- 調査員が申請者の自宅などに訪問し、心身の状況を調査します。
「認定調査を受けられる方へ(PDFファイル:232.3KB)」をご覧ください。 - 市から主治医へ意見書の作成を依頼します。
3 審査・判定
- 認定調査の結果をコンピュータで判定します。(一次判定)
- 一次判定結果、主治医意見書、特記事項をもとに、介護認定審査会で審査・判定します。(二次判定)
特記事項とは…認定調査員が、申請者の状態について記載するもので、具体的な「介護の手間と頻度」等を記載するもの
4 認定・通知
- 審査会における二次判定により、「要介護1~5」「要支援1・2」「非該当」の区分に認定されます。
- 市から認定結果を通知します。
◆申請から30日以上経過するとき…「介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書」が届きます。
認定は、原則として申請受理後30日以内に行いますが、30日以上を要する場合は、延期理由を記載した「認定延期通知書」にてお知らせします。
なお、認定延期通知書が届いた場合、新たに手続きをいただく必要はありません。
更新申請については、有効期間内に認定を行うことができる場合、認定延期通知を省略します。
ケアプランの作成依頼
要介護(要支援)認定を受けた方は、介護区分に応じサービスを利用することができます。
- 「要介護1~5」の認定を受けた人…居宅介護支援事業者にケアプランの作成を依頼してください。
- 「要支援1・2」の認定を受けた人…地域包括支援センターまたは指定を受けた居宅介護支援事業者にケアプランの作成を依頼してください。
- 判定結果が「非該当」の人…介護保険のサービスは利用できませんが、生活機能の低下がみられた場合に利用できるサービスがあります。地域包括支援センターに相談してください。
地域包括支援センター・居宅介護支援事業所の連絡先
要介護(要支援)認定申請やケアプラン作成・サービス利用に関する相談は、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所で行っています。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 福祉課 介護認定審査係
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-755-5667
ファックス番号:025-757-3800
メールでのお問い合わせはこちら
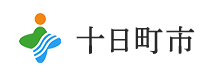
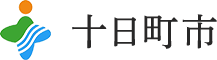
更新日:2025年03月31日