高額療養費の支給
1か月に医療機関などへ支払った自己負担額(注釈1)が自己負担限度額を超えた場合、申請により限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。高額療養費の支給対象となる世帯には通知によりお知らせします(注釈2)。
(注釈1)入院時の食事代や居住費、差額ベッド代、保険適用外の医療費などは高額療養費の対象になりません。
(注釈2)国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する申請書を提出した世帯には通知されません。
自己負担限度額
70歳未満の自己負担限度額(月額)
| 所得(注釈3)要件 | 区分 | 自己負担限度額(月額) | 4回目以降(注釈5) |
|---|---|---|---|
|
901万円を超える |
ア | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1パーセント | 140,100円 |
| 600万円を超え901万円以下 | イ | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1パーセント | 93,000円 |
| 210万円を超え600万円以下 | ウ | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1パーセント | 44,400円 |
| 210万円以下(住民税非課税世帯を除く) | エ | 57,600円 | 44,400円 |
| 住民税非課税世帯(注釈4) | オ | 35,400円 | 24,600円 |
(注釈3)所得とは、世帯の国民健康保険加入者全員の前年(受診月が1月から7月までの場合は前々年)の総所得金額などから基礎控除額を差し引いた額を合計した額です。なお、所得未申告者がいる世帯は区分アに含まれます。
(注釈4)住民税非課税世帯とは、世帯主(国民健康保険に加入していない場合も含みます)と世帯の国民健康保険加入者全員が、受診した月の属する年度(4月から7月までは前年度)の住民税が非課税の世帯です。
(注釈5)4回目以降の金額は、過去12か月以内に4回以上高額療養費の支給があった場合の自己負担限度額です。
70歳以上75歳未満の自己負担限度額(月額)
70歳未満の方とは別に自己負担限度額が決められており、外来(個人単位)の自己負担額も設けられています。
| 所得要件 | 区分 | 外来(個人ごと) | 外来+入院(世帯) |
|---|---|---|---|
| 同一世帯内に70歳以上の国民健康保険加入者で住民税課税所得が690万円以上の方がいる | 現役並み所得者3 |
252,600円+(実際にかかった医療費-842,000円)×1パーセント (140,100円)(注釈6) |
|
| 同一世帯内に70歳以上の国民健康保険加入者で住民税課税所得が380万円以上の方がいる | 現役並み所得者2 |
167,400円+(実際にかかった医療費-558,000円)×1パーセント (93,000円)(注釈6) |
|
| 同一世帯内に70歳以上の国民健康保険加入者で住民税課税所得が145万円以上の方がいる | 現役並み所得者1 |
80,100円+(実際にかかった医療費-267,000円)×1パーセント (44,000円)(注釈6) |
|
| 区分が現役並所得者・低所得者以外 | 一般 |
18,000円 (年間上限144,000円)(注釈7) |
57,600円 (44,000円)(注釈6) |
| 同一世帯の世帯主と国民健康保険被保険者の全員が住民税非課税で、低所得者1以外 | 低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 |
| 同一世帯の世帯主と国民健康保険被保険者の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費及び控除を差し引いたとき0円となる | 低所得者1 | 8,000円 | 15,000円 |
(注釈6)( )内は過去12か月以内に4回以上高額療養費の支給があった場合の4回目以降の限度額です。ただし、外来(個人ごと)の自己負担限度額を超えたことによる高額療養費の支給は回数に含みません。
(注釈7)外来(個人ごと)の自己負担額には、年間で144,000円の自己負担上限額が設定されています。(外来年間合算)
75歳到達月の自己負担限度額の特例について
国民健康保険加入者で月の途中(注釈8)に75歳になった方は、国民健康保険と後期高齢者医療制度において、制度が移行した月の医療費の自己負担限度額がそれぞれ2分の1となります。
また、月の途中に75歳となり、社会保険など(国民健康保険組合も含む)から後期高齢者医療制度に移行した方の被扶養者で、国民健康保険に移行した方についても、制度が移行した月の自己負担限度額がそれぞれ2分の1となります。
(注釈8)月の途中とは、2日から月の末日のことを言います。
医療機関の窓口での支払いを限度額までに抑えるための手続き
入院、外来などで医療費が高額になる場合、以下の方法で支払いを自己負担限度額までに抑えることができます。
オンライン資格確認
マイナ保険証で受診することで、1つの医療機関での外来や入院で、1か月あたりの医療費の一部負担金の支払いが自己負担額までとなり、住民税非課税世帯の人は入院中の食事代も減額されます。
資格確認書による受診においても、オンライン資格確認による限度額の確認に同意することで、限度額適用認定証を掲示することなく限度額が適用されます。
ただし、区分が「オ」または「低所得2」の方で、過去12か月間に90日を超える入院があり、入院中の食事代を更に減額する場合は、別途「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要になります。
限度額適用認定証等
上記、オンライン資格確認ができない医療機関を受診する場合や「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要な場合は申請が必要です。
- 適用日は申請月の1日からとなりますので事前に申請してください。
- 保険料を滞納している場合、原則として交付されません。
【申請に必要なもの】
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
高額療養費の計算のしかた
| 暦月ごとに計算 | 月の初日から月末までの受診について、1か月として計算します。 |
| 病院・診療所ごとに計算 | 1つの病院・診療所ごとに計算します。 |
| 入院と外来 | 同一の病院・診療所でも、入院と外来は別々に計算します。 |
| 院外処方にて薬剤費を支払ったとき | 処方せんを発行した病院・診療所の外来の自己負担額と合算して計算します。 |
| 医科と歯科 | 同一の病院・診療所に医科と歯科がある場合であっても、医科と歯科は別々に計算します。 |
| 療養費の自己負担分 | 高額療養費の対象となる場合があります。 |
| 入院時の食事代や居住費 | 高額療養費の計算対象外です。 |
| 差額ベッド代など | 高額療養費の計算対象外です。 |
| 保険適用外の医療費 | 高額療養費の計算対象外です。 |
70歳未満の方の計算
同じ月に複数の医療機関で自己負担額を支払った場合や、同じ世帯の別の国民健康保険加入者が医療機関で自己負担額を支払った場合は、それぞれの自己負担額を合計して高額療養費の計算をすることができます。
70歳未満の人は、個人ごと、医療機関ごとの自己負担額が21,000円以上の場合に高額療養費の計算に含めることができます。
70歳以上75歳未満の方の計算
同じ月に複数の医療機関で自己負担額を支払った場合や、同じ世帯の別の70歳以上75歳未満の国民健康保険加入者が医療機関で自己負担額を支払った場合は、それぞれの自己負担額を合計して高額療養費の計算をします。
70歳未満の人とは異なり、70歳以上75歳未満の人は全ての自己負担額を合計することができます。
外来(個人ごとに計算)
個人で1か月に外来で支払った全ての自己負担額を合計し、外来(個人単位)の限度額を超えた場合、超えた額が支給されます。
外来と入院がある場合(世帯単位)
世帯の70歳以上75歳未満の国民健康保険加入者が同じ月に外来や入院で支払った全ての自己負担額を合計し、外来+入院(世帯)の限度額を超えた場合に、超えた額が支給されます。
70歳未満の方と70歳以上75歳未満の方が同じ世帯の場合の計算
70歳未満の方と70歳以上75歳未満の方で世帯合算する場合は、70歳以上75歳未満の方の外来分・入院分をそれぞれ計算し、その後70歳未満の方の21,000円以上(医療機関、入院、外来、医科、歯科別)の一部負担金を合わせて、70歳未満の方の自己負担限度額を超えた場合に高額療養費を支給します。
申請に必要なもの
- 国民健康保険高額療養費支給申請書(診療月の概ね3か月後を目途に、支給対象となる世帯に送付します。)
- 振込先口座のわかるもの(預金通帳等)
- 領収書(原本)
高額療養費の支給申請手続きの簡素化
令和6年4月から高額療養費支給申請手続の簡素化(以下「簡素化」という。)を開始しました。これまでは、診療月ごとに申請書の提出や領収書の確認が必要でしたが、簡素化の手続きを行うことで、手続き以降に高額療養費に該当した場合の申請書の提出や領収書の確認が不要になり、自動的に指定口座へ振込(支給)することができるようになります。
(注意)令和6年4月以前に案内をした高額療養費や、簡素化の手続きを行う前の高額療養費は、従来の診療月ごとの支給申請が必要です。
簡素化の申請に必要なもの
簡素化を希望する場合は「国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する申請書」を提出してください。
国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する申請書 (PDFファイル: 108.9KB)
簡素化の停止
以下の項目に該当した場合は簡素化が停止となります。
- 国民健康保険世帯主の資格に異動があり、要件を満たさなくなった場合
- 指定した振込先金融機関口座に高額療養費の振込みができなくなった場合
- 簡素化をした方が死亡した場合
- 国民健康保険税の滞納がある場合(注釈9)
- 申請の内容に偽りその他不正があった場合
- 市長が適当でないと認めた場合
(注釈9)滞納が解消された場合は簡素化を再開します。
高額療養費の外来年間合算
外来年間合算とは
8月1日から翌年7月31日(以下「計算期間」という。)の間に70歳以上75歳未満である方の、1年間にかかった外来診療の自己負担額を個人単位で合算し、144,000円を超えた場合は、申請によりその超えた金額を支給します。
支給対象となる世帯には通知によりお知らせします。
支給対象
高額療養費(外来年間合算)の支給の対象となるのは、次の全てに該当する人です。
- 計算期間に70歳以上75歳未満の人(注釈10)
- 基準日(7月31日)時点で所得区分が「一般」「低所得者1」「低所得者2」の人(注釈11)
- 計算期間にかかった外来診療の自己負担額が144,000円を超える人(注釈12)
(注釈10)計算期間中に70歳となった場合、69歳であった月までの自己負担額は含みません。
(注釈11)基準日(7月31日)時点で高額療養費の所得区分が「現役並み所得者」に該当している人は、高額療養費(外来年間合算)の対象にはなりません。
(注釈12)外来診療の自己負担額は、個人ごとに計算します。
時効について
高額療養費の支給を受ける権利の消滅時効は、診療を受けた月の翌月の初日から2年です。この2年間の消滅時効にかかっていない高額療養費であれば、過去にさかのぼって支給申請をすることができます。
この記事に関するお問い合わせ先
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-757-3735
年金担当ダイヤル:025-757-3748
ファックス番号:025-752-6924
メールでのお問い合わせはこちら
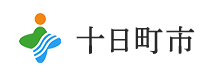
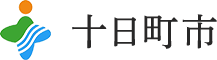
更新日:2025年08月01日