国民健康保険税について
国民健康保険税は世帯単位で計算され、「医療分」と「支援分」と「介護分」の合算額で算定します。
医療分・支援分の税率(令和7年度)
| 所得割額[医療分(6.0%)] | 加入者の前年中の総所得金額等から住民税基礎控除額を差し引き、その額に税率を掛けた額 |
|---|---|
| 所得割額[支援分(2.5%)] | 加入者の前年中の総所得金額等から住民税基礎控除額を差し引き、その額に税率を掛けた額 |
| 被保険者均等割額 [医療分(24,500円)] |
加入者の人数に応じて一人あたりいくらと計算した額 |
| 被保険者均等割額 [支援分(14,100円)] |
加入者の人数に応じて一人あたりいくらと計算した額 |
| 世帯別平等割額[医療分(17,500円)] | 各世帯均一の額 |
- 医療分・支援分の額は所得割額、被保険者均等割額、世帯別平等割額の合計です。
- 令和6年度から据置きです。
介護分の税率(令和7年度)
| 所得割額 (1.8%) |
加入者の前年中の総所得金額等から住民税基礎控除額を差し引き、その額に税率を掛けた額 |
|---|---|
| 被保険者均等割額 (13,600円) |
介護保険第2号被保険者の人数に応じて一人あたりいくらと計算した額 |
- 介護分の額は所得割額、被保険者均等割額の合計です。
- 介護分は介護保険2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)に賦課されます。
- 令和6年度から据置きです。
課税限度額(令和7年度)
| 医療分 | 660,000円 |
|---|---|
| 支援分 | 260,000円 |
| 介護分 | 170,000円 |
国民健康保険税の内訳
| 40歳未満の方 | 医療分+支援分 |
|---|---|
| 40歳以上65歳未満の方 | 医療分+支援分+介護分 |
| 65歳以上75歳未満の方 | 医療分+支援分 (別途、介護保険料を納付します) |
国民健康保険税の計算例
2人暮らしの給与所得世帯の場合
- 世帯の中の国民健康保険加入者:2人(夫:50歳で収入あり、妻:48歳で収入なし)
- 給与収入:320万円(給与所得控除前)
- 給与所得:216万円
医療給付分
- 所得割 → (216万円-住民税基礎控除43万円)×6.0%=103,800円
- 被保険者均等割 → 2人×24,500円=49,000円
- 世帯別平等割 → 17,500円
合計=170,300円(A)(100円未満切り捨て)
(注意)計算された医療給付分の合計が66万円を超えたときは、66万円となります。
後期支援分
- 所得割 → (216万円-住民税基礎控除43万円)×2.5%=43,250円
- 被保険者均等割 → 2人×14,100円=28,200円
合計=71,450円(B)(100円未満切捨)
(注意)計算された後期支援分の合計が26万円を超えたときは、26万円となります。
介護納付分
- 所得割 → (216万円-住民税基礎控除43万円)×1.8%=31,140円
- 被保険者均等割 → 2人×13,600円=27,200円
合計=58,340円(C)(100円未満切捨)
(注意)計算された介護納付分の合計が17万円を超えたときは、17万円となります。
- 世帯の国民健康保険税の合計:(A)+(B)+(C)=300,090円
国民健康保険税の納め方
各月末(休日や祝日の場合は直後の平日)を納期限とした年9回です。各月15日頃に送られる納付書を使い金融機関の窓口でお支払ください。また、口座振替の方は指定した金融機関から引き落としになります。
| 第1期 | 7月16日から7月31日 |
|---|---|
| 第2期 | 8月16日から8月31日 |
| 第3期 | 9月16日から9月30日 |
| 第4期 | 10月16日から10月31日 |
| 第5期 | 11月16日から11月30日 |
| 第6期 | 12月16日から12月31日 |
| 第7期 | 1月16日から1月31日 |
| 第8期 | 2月16日から2月末日 |
| 第9期 | 3月16日から3月31日 |
(注意)納期限の日が休日や祝日の場合は繰り下がります。
(注意)納めた国民健康保険税は所得税や住民税の申告の際に、社会保険料控除の対象になります。
特別徴収(年金からの天引き)について
特別徴収(年金からの天引き)の対象の世帯は世帯主の年金から国民健康保険税が天引きで徴収されます。
対象世帯は、次の要件をすべて満たす世帯です。
- 世帯主が国民健康保険の加入者であること
- 世帯内の国民健康保険加入者全員が、65歳以上75歳未満であること
- 特別徴収対象年金の年額が18万円以上であること
- 介護保険料が天引きされている年金が対象で、国民健康保険税と介護保険料の合計が、年金額の2分の1を超えないこと
(注意)特別徴収に切り替わっても、世帯の国民健康保険税の年額は変わりません。
申し出をすることによって口座振替による納付に変更できます。
特別徴収から口座振替に変更を希望される方は、申請が必要になります。
【申請ができる世帯】
- これまでの国民健康保険税を完納していること
- これからの国民健康保険税を口座振替で納付すること
【持参するもの】
- 『口座振替依頼書』の本人控え
(注意)すでに口座振替を利用されている場合は、『口座振替依頼書』の本人控えは不要です。
国民健康保険税の通知
世帯主が納税義務者です。世帯の中に国民健康保険加入者がいるとき、国民健康保険税は世帯主が納めることになります。7月の本算定により国民健康保険税が決まりましたら通知書でお知らせします。年度の途中で職場の健康保険に加入または脱退したときは、届出を受けた翌月に再計算し、その内容を変更(決定)通知書でお知らせします。
国民健康保険税の軽減制度
低所得者世帯に係る軽減制度
世帯主と世帯に属する被保険者と世帯に属する特定同一世帯所属者(注釈1)の前年中の総所得金額等が下記の軽減基準所得以下の場合、均等割・平等割が軽減されます。(申請不要)
| 軽減割合 | 軽減基準所得 | (例)3人(給与所得者等(注釈2)の人数が2人)の場合 |
|---|---|---|
| 2割 |
43万円+56万円×被保険者と特定同一世帯所属者(注釈1)の人数+10万円×(給与所得者等(注釈2)の数-1)(注釈3) |
221万円 |
| 5割 | 43万円+30.5万円×被保険者と特定同一世帯所属者(注釈1)の人数+10万円×(給与所得者等(注釈2)の数-1)(注釈3) | 144.5万円 |
| 7割 | 43万円+10万円×(給与所得者等(注釈2)の数-1)(注釈3) | 53万円 |
(注釈1)特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療保険に移行し、継続して同一の世帯に属する人をいいます。
(注釈2)納税義務者、世帯内の被保険者、特定同一世帯所属者のうち、一定の給与所得者並びに公的年金等受給者をいいます。
(注釈3) 軽減基準所得の計算式の中の『+10万円×(給与所得者等(注釈2)の数-1)』の計算については、給与所得者等の数が2人以上の場合に適用されます。
(注釈4)この判定には、住民税の所得を用いるため、未申告の場合は、軽減の判定ができなくなります。そのため、収入のない人でも申告が必要です。ただし、所得税の申告をした人は、改めて申告する必要はありません。
未就学児の均等割軽減制度
国保に加入する未就学児の均等割(医療分+支援分)を一律5割軽減します。上記の低所得世帯に対する軽減制度に該当する場合は、その軽減後の額をさらに5割軽減します。(申請不要)
産前産後期間の軽減制度
出産する予定または出産した方の産前産後期間相当分の所得割・均等割を軽減する制度があります。軽減を受けるには、原則として申請が必要です。
【対象となる方】
国民健康保険の被保険者で、妊娠85日(4か月)以上の出産をする(した)お母さんが対象です。(死産、流産、人工妊娠中絶の場合も含みます。)
【軽減期間】
出産予定日または出産日が属する月の前月から翌々月までの4か月間
(注意)多胎妊娠(2人以上の赤ちゃんを同時に妊娠)の場合は出産予定日または出産日が属する月の3か月前から翌々月までの6か月間
【申請方法】
出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
以下をご用意のうえ窓口までお越しください。
- 母子健康手帳
- 窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
(注意)出産被保険者と住民票上、別世帯の方が届出をする場合は、委任状が必要です。
非自発的失業者の軽減制度
会社の倒産、解雇、雇い止め等により離職した人については、条件を満たすことにより国民健康保険税が軽減される制度があります。軽減を受けるには申請が必要です。
【対象となる方】
以下のすべてを満たす人が軽減の対象者となります。
- 雇用保険受給資格者証(または雇用保険受給資格通知)で、特定受給資格者または特定理由離職者と確認できる人(雇用保険受給資格者証の離職理由が11、12、21、22、23、31、32、33、34のいずれかの人)
- 離職時点で65歳未満の人
【軽減内容】
離職日の翌日の属する年度の翌年度末までの期間、対象者の前年の給与所得を100分の30とみなして算定することにより、国民健康保険税を軽減します。
【申請方法】
雇用保険受給資格者証(紛失などの場合には、ハローワークへお問い合わせください)をご用意のうえ窓口までお越しください。
国民健康保険税の減免制度
旧被扶養者の減免制度
会社の健康保険などの被保険者本人が後期高齢者医療制度に移行することにより、被扶養者だった65歳以上の方(旧被扶養者)が国保に加入する場合、申請により減免措置が受けられます。
【対象となる方】
以下のすべてを満たす人が減免の対象者となります。
- 会社の健康保険などから後期高齢者医療制度に移行することにより、国保に加入した扶養親族の方
- 加入時点で65歳以上75歳未満の方
【減免内容】
所得割:当分の間、免除となります。
均等割:加入から2年(24か月)を経過する月まで5割減免となります。
平等割:(国保加入者が旧被扶養者だけの世帯の場合)加入から2年(24か月)を経過する月まで5割減免となります。
【申請方法】
対象となる方にご連絡いたします。
その他の減免制度
次の理由に該当し、国民健康保険税を納付することが著しく困難であるという世帯については、国民健康保険税が減免される場合があります。
- 震災、風水害、火災その他の災害により住宅、家財などが著しい損害を受けた世帯
- 倒産、廃業、休業、失業、疾病その他の理由により所得が著しく減少した世帯
- その他特別な事情があると認められる世帯
(注意)なお、減免申請の理由により提出していただく確認資料がありますので、詳しくはお問い合わせください。
国民健康保険税を納めずにいると
特別の事情なく国民健康保険税を滞納すると、療養の給付等に代わり特別療養費が支給され、医療費を一旦全額自己負担していただくなどの処分を受けることがあります。
さらに滞納が続くと、保険給付の差し止め、財産の差押処分を受ける場合があります。納付が困難な場合は早めにご相談ください。
納付は口座振替で
国民健康保険税の納付は、安全で便利な口座振替をお勧めします。手続きは次の金融機関でできます。その際、口座の印鑑が必要です。
- 第四北越銀行
- 大光銀行
- 魚沼農業協同組合
- ゆうちょ銀行
- 新潟県労働金庫
- 新潟県信用組合
この記事に関するお問い合わせ先
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-757-3735
年金担当ダイヤル:025-757-3748
ファックス番号:025-752-6924
メールでのお問い合わせはこちら
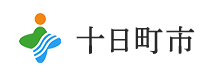
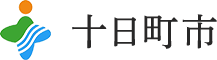
更新日:2025年04月01日