後期高齢者医療制度
75歳以上(一定の障がいのある方は65歳以上)の方を対象とする医療制度です。
新潟県内のすべての市町村が加入する「新潟県後期高齢者医療広域連合」が運営主体です。
- 広域連合は、被保険者の資格管理、保険料の賦課、医療給付等を行います。
- 市町村は、住民の利便性確保のため、申請書の受付等の窓口業務や保険料の徴収業務を行います。
詳しくは、新潟県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部リンク)をご確認ください。
マイナ保険証について
2024年12月2日に従来の保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しました。診療履歴に基づいたより良い医療が受けられるなどのメリットがあるマイナ保険証をぜひご利用ください。
まだマイナ保険証を持っていない人は「資格確認書」でこれまでどおりの医療を受けることができますので、ご安心ください。
「資格確認書」の交付
後期高齢者医療制度において、マイナ保険証を基本とする仕組みの円滑な移行に向けた対応として、デジタルとアナログの併用期間を確保する観点から、令和6年12月2日以降、新規加入者及び券面情報に変更が生じた者について、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、資格確認書(従来の保険証にかわるもの)を交付します。
詳しくは、新潟県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部リンク)をご確認ください。
被保険者(加入する方)
75歳以上の方
【資格取得日】
75歳の誕生日(加入手続きは必要ありません。)
65歳から74歳までの方で一定の障害のある方
【対象者】
- 身体障害者手帳1~3級
- 身体障害者手帳4級のうち、音声機能障害・言語機能障害・下肢障害の1・3・4号
- 療育手帳「A」
- 精神障害者保健福祉手帳1~2級
- 国民年金証書(障害年金1~2級)
【資格取得日】
- 申請日の翌日
【申請に必要なもの】
- 障がいの程度を証明するもの(身体障害者手帳、精神保健福祉手帳、障害年金証書、医師の診断書等)
医療費の自己負担割合(病院にかかったときに支払う費用)
| 所得区分 | 負担割合 | 該当条件 |
|---|---|---|
| 現役並み所得者 | 3割 |
住民税課税所得が145万円以上の被保険者及びその被保険者と同じ世帯の被保険者。 ただし、下記に該当する方は「一般1」または「一般2」の区分となります。
|
| 一般2 |
2割 |
住民税課税所得が28万円以上の被保険者及びその被保険者と同じ世帯の被保険者のうち、
|
| 一般1 | 1割 | 住民税課税世帯で同一世帯に「現役並み所得者」及び「一般2」に該当する被保険者がいない方 |
| 区分2 | 1割 | 世帯全員が住民税非課税で、「区分1」以外の方 |
| 区分1 | 1割 |
世帯全員が住民税非課税で、かつ世帯全員が1または2に該当する方
|
(注釈1) 年金収入には遺族年金、障害年金は含みません。
(注釈2)(年金収入-806,700万円)は、年金収入が806,700万円未満の時は0円として計算します。
■以下の場合は、保険適用できません。
- 病気とみなされないとき
日常生活における疲労や肩こり、健康診断、人間ドック、予防接種、歯列矯正、美容整形など - 給付が制限されるとき
故意の犯罪行為や故意の事故、けんかや泥酔による病気やけが、医師や保険者の指示に従わなかったとき - 他の制度の対象となるとき
仕事中や勤務途上に起きた負傷(労災保険の対象となります)など - その他
症状の改善がみられない長期の施術、脳疾患後遺症などの慢性病
医療費が高額になったとき
高額療養費の支給
医療機関の窓口では、かかった医療費の1割から3割を自己負担額として支払います。
ただし、1か月(同じ月内)の医療費の自己負担額が下記の限度額を超えた場合は、申請により超えた分が「高額療養費」として支給されます。
対象となる方には、受診月のおおむね3か月後に「後期高齢者医療高額療養費支給申請書」を送付します。本庁市民生活課または各支所地域振興課市民係へ申請してください。
また、一度申請をすれば、再度申請していただく必要はありません。その後も支給対象になった場合は継続して指定口座に支給されます。
(注意)入院時の食事代や医療保険が適用されない部分(差額ベッド料など)は対象となりません。
【申請に必要なもの】
- 後期高齢者医療高額療養費支給申請書
- 資格確認書
- 預金通帳などの口座がわかるもの
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
自己負担限度額(月額)
自己負担額は、外来(個人単位)を適用後に外来+入院(世帯単位)を適用します。
(注意)自己負担額は、病院・診療所・歯科・調剤の区別なく合算できます。ただし、入院時の食事代や医療保険のきかない費用(差額ベッド代など)は合算できません。
■窓口負担割合が2割負担の方への配慮措置が終了します。
令和7年9月30日までの診療分をもちまして、窓口負担割合が2割負担の方の1ヶ月の外来診療での窓口負担を、1割負担の額から3,000円以内の増加額に抑える配慮措置が終了となります。
本措置の終了に伴い、令和7年10月1日以降の外来診療分につきましては、医療機関での窓口負担がこれまでよりも増えることや、高額療養費等の給付額が少なくなる可能性があります。
制度改正についての問い合わせ窓口として、厚生労働省がコールセンターを設置しておりますのでご活用ください。
【厚生労働省コールセンター】
・電話番号 0120-117-571(フリーダイヤル)
・設置期間 令和7年7月1日(火曜日)~令和8年3月31日(火曜日)
※日曜日、祝日、年末年始は除く
・対応時間 午前9時~午後6時
|
所得区分 |
外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
|---|---|---|
| 現役並み所得者3 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% (140,100円(注釈1)) |
|
| 現役並み所得者2 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% (93,000円(注釈1)) |
|
| 現役並み所得者1 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% (44,400円(注釈1)) |
|
|
一般2 一般1 |
18,000円 (年間上限144,000円(注釈4)) |
57,600円 (44,400円(注釈2)) |
| 区分2 | 8,000円 | 24,600円 |
| 区分1 | 8,000円 | 15,000円 |
|
所得区分 |
外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
|---|---|---|
| 現役並み所得者3 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% (140,100円(注釈1)) |
|
| 現役並み所得者2 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% (93,000円(注釈1)) |
|
| 現役並み所得者1 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% (44,400円(注釈1)) |
|
| 一般2 | 18,000円 または6,000円+(医療費(注釈3)-30,000円)×10%の低い方 (年間上限144,000円(注釈4)) |
57,600円 (44,400円(注釈2)) |
| 一般1 | 18,000円 (年間上限144,000円(注釈4)) |
57,600円 (44,400円(注釈2)) |
| 区分2 | 8,000円 | 24,600円 |
| 区分1 | 8,000円 | 15,000円 |
(注釈1)過去12ヵ月以内に高額療養費の支給を3回受けたときの4回目以降の限度額
(注釈2)過去12か月以内に「外来+入院(世帯単位)」の高額療養費の支給を3回受けたときの4回目以降の限度額
(注釈3)医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算
(注釈4)1年間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)のうち所得区分が「一般1・一般2」または「区分1・区分2」であった月の外来(個人単位)の自己負担額の合計額の上限額
自己負担額の計算
- 個人単位:外来分のみで自己負担額の合計額を計算し、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
- 世帯単位:個人単位を計算した後、入院分を含めた世帯(後期高齢者医療制度被保険者のみ)の自己負担額を計算し、限度額を超えた分がかかった医療費に応じて按分され、被保険者それぞれに高額療養費として支給されます。
- 75歳の誕生月については、加入前の保険等後期高齢者医療制度の自己負担額がそれぞれ2分の1となります(障害認定により加入された方は2分の1にはなりません)。
入院時の食事代
入院したときの食事代は、医療費とは別に定額の自己負担となります。また、療養病床に入院したときは、食事代と居住費の一部が自己負担となります。
区分1及び区分2の方は、入院の際に「マイナ保険証」を利用、または「任意記載事項を併記した資格確認書」を提示すると、食事代の負担額が下表のとおり減額されます。
(注意)食事代1食当たりの金額は、令和7年4月より10~20円の引き上げとなりました。
一般病床入院時の食事代の自己負担額
| 所得区分 | 1食あたりの食事代 | |
|---|---|---|
| 一般、現役並み所得者 | 490円(注釈1) | |
| 区分2 | 過去12か月で90日までの入院 | 230円 |
| 過去12か月で90日を超える入院 | 180円(注釈3) | |
| 区分1 | 110円 | |
(注釈1)特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの方は280円
| 所得区分 | 1食あたりの食事代 | |
|---|---|---|
| 一般、現役並み所得者 | 510円(注釈2) | |
| 区分2 | 過去12か月で90日までの入院 | 240円 |
| 過去12か月で90日を超える入院 | 190円(注釈3) | |
| 区分1 | 110円 | |
(注釈2)特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの方は300円
(注釈3)過去12か月の「区分2」の入院日数が90日(後期高齢者医療制度に加入する前の保険も含む)を超えた場合、申請いただくことで「長期入院該当」となり、91日目以降の食事代がさらに減額されます。
【長期入院の申請に必要なもの】
- 本人確認書類
- 資格確認書
- 医療機関が発行する入院時の領収書
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
療養病床入院時の食事代・居住費の自己負担額
| 所得区分 | 1食あたりの食事代 | 1日あたりの居住費 |
|---|---|---|
| 一般、現役並み所得者 | 490円(注釈1) | 370円 |
| 区分2 | 230円 | 370円 |
| 区分1 | 140円 | 370円 |
| 区分1(老齢福祉年金受給者) | 110円 | 0円 |
(注釈1)一部医療機関では450円
| 所得区分 | 1食あたりの食事代 | 1日あたりの居住費 |
|---|---|---|
| 一般、現役並み所得者 | 510円(注釈2) | 370円 |
| 区分2 | 240円 | 370円 |
| 区分1 | 140円 | 370円 |
| 区分1(老齢福祉年金受給者) | 110円 | 0円 |
(注釈2)一部医療機関では470円
療養病床に入院したときは、介護保険で入院している方との負担の均衡を図るため、上記のとおり定められた食費と居住費が自己負担となります。
医療費と介護保険サービス利用料が高額になったとき
同じ世帯で1年間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)の医療費と介護保険サービス料の自己負担額の合計が下記の限度額を超えた場合には、申請により超えた分が「高額介護合算療養費」として支給されます。支給の対象となる方には、高額介護合算療養費等支給申請書を送付します。
(注意)高額介護合算療養費は、支払った自己負担額の割合で後期高齢者医療制度と介護保険制度、それぞれの保険者から支払われます
| 所得区分 | 自己負担限度額 |
|---|---|
| 現役並み所得者3 | 2,120,000円 |
| 現役並み所得者2 | 1,410,000円 |
| 現役並み所得者1 | 670,000円 |
| 一般1・一般2 | 560,000円 |
| 区分2 | 310,000円 |
| 区分1 | 190,000円 |
限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証
後期高齢者医療制度の限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証は、令和6年12月2日から新規発行されなくなり、以下のとおりとなります。
「マイナ保険証」を利用する方
「マイナ保険証」を利用すると、手続きなしで、1医療機関・薬局当たりのひと月の保険適用の医療費等の支払いが自己負担限度額までになります。
「マイナ保険証」を利用しない方
令和6年12月2日以降は、認定証に代わり、資格確認書の「任意記載事項」を併記することで、1医療機関・薬局当たりのひと月の保険適用の医療費等の支払いが自己負担限度額までになります。
以下のものを持参の上、本庁市民生活課または各支所地域振興課市民係へ申請してください。
【申請に必要なもの】
- 本人確認書類
- 資格確認書
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
特定疾病療養受療証
厚生労働大臣が指定する特定疾病(次の1~3のいずれか)の場合には、患者負担の毎月の限度額は1医療機関(入院・外来別)につき10,000円です。
特定疾病によるこの適用を受けるには、「特定疾病療養受療証(注釈1)」が必要です。
以下のものを持参の上、本庁市民生活課または各支所地域振興課市民係へ申請してください。
(注釈1)資格確認書に特定疾病の区分を併記することも可能です。
【特定疾病の認定対象者】
1、人口透析が必要な慢性腎不全
2、血友病
3、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
【発行期日】
- 申請月の1日から
【申請に必要なもの】
- 資格確認書
- 医師の意見書または国民健康保険等の特定疾病療養受療証
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
申請後に受けられる給付
葬祭費の支給
被保険者が亡くなったときは、葬祭を行った方(喪主)に葬祭費50,000円が支給されます。
以下のものを持参の上、本庁市民生活課または各支所地域振興課市民係へ申請してください。
【申請に必要なもの】
- 亡くなった方の資格確認書
- 葬祭を行った方(喪主)の預金通帳などの振込先口座がわかるもの
- 葬祭を行った事実確認ができるもの(領収書、会葬礼状等)
コルセット等の治療用装具代の支給
医師の指示により、コルセット等の補装具を作ったときは、いったん全額負担しますが、後から申請して認められると自己負担分(医療費の1割から3割)以外が療養費として支給されます。
【申請に必要なもの】
- 資格確認書
- 医師の証明書
- 治療用装具の領収書
- 預金通帳などの口座がわかるもの
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
はり・灸・マッサージ等の施術を受けたとき
医師が必要と認めた、はり・灸・マッサージ等の施術を受けたり、骨折や捻挫等で保険を扱っていない柔道整復師の施術を受けたときは、後から申請して認められると自己負担分(医療費の1割から3割)以外が療養費として支給されます。
【申請に必要なもの】
- 資格確認書
- 医師の証明書
- 診療施術の明細書
- 預金通帳などの口座がわかるもの
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
移送費の支給
医師の指示による一時的・緊急的な必要性があり、重病人の入院・転院等で移送の費用がかかったときは、広域連合の承認が得られた場合に限り、移送にかかった費用が支給されます。
【申請に必要なもの】
- 資格確認書
- 医師の意見書
- 費用の領収書
- 預金通帳などの口座がわかるもの
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
保険料の計算方法
保険料(年額)は前年中の総所得金額などをもとに個人単位で賦課されます。1人あたりの賦課限度額は80万円です。
保険料(年額)は加入者の所得に応じて決まる「所得割額」と加入者が等しく負担する「均等割額」の合計となります。
保険料率
| 所得割額 | 8.61% |
|---|---|
| 均等割額(年額) | 44,200円 |
1人あたりの保険料額の計算方法
1人あたりの保険料(年額)は「所得割額」と「均等割額」を合計した額(100円未満切り捨て)となります。
| 所得割額 | 前年中の総所得金額から基礎控除額を引いた額に所得割率(8.61%)をかけた額 |
|---|---|
| 均等割額 | 1人あたり44,200円 |
| 被保険者本人の合計所得金額 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 2,400万円以下 | 43万円 |
| 2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 |
| 2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 |
| 2,500万円超 | 0円 |
ただし、所得の低い世帯の方は「均等割額」が軽減となります。
軽減割合は、同一世帯内の加入者および世帯主(加入者でない方も含む)の所得金額の合計をもとに次の基準により判定します。
均等割額の軽減対象判定基準
- 軽減判定時の年金所得計算方法
年金所得=(年金収入-公的年金等控除)-特別控除15万円(65歳以上のみ)
| 均等割額軽減割合 | 同一世帯の加入者および世帯主の合計所得金額 | 軽減後の年額 |
|---|---|---|
| 7割軽減 |
43万円+10万円×(給与所得者等(注釈1)の数-1)以下の場合 |
13,260円 |
| 5割軽減 |
43万円+30.5万円×世帯の被保険者の数+10万円×(給与所得者等(注釈1)の数-1)以下の場合 |
22,100円 |
| 2割軽減 |
43万円+56万円×世帯の被保険者数+10万円×(給与所得者等(注釈1)の数-1)以下の場合 |
35,360円 |
「10万円×(給与所得者等(注釈1)の数-1」の計算は、同一世帯の被保険者と世帯主に給与所得者等(注釈1)が2人以上いる場合に計算します。
(注釈1)給与所得者等とは以下の方であり、給与と年金の両方に該当する場合は1人と数えます。
- 給与の収入額が55万円を超える方
- 公的年金の収入額が65歳未満で60万円を超える方
- 公的年金の収入額が65歳以上で125万円を超える方
加入前日において被用者保険の被扶養者であった方への軽減
制度加入前日において保険料負担のなかった被用者保険の被扶養者であった方は、保険料の「均等割額」が資格所得月から2年間のみ5割軽減され、「所得割額」はかかりません。
軽減後の年間保険料額は22,100円です。(市町村国保や国保組合などは対象となりません。)
保険料の納め方
年金から天引きされる「特別徴収」と納付書や口座振替で納める「普通徴収」があります。
特別徴収(年金からの天引き)
下記の3つに該当する方が特別徴収対象者になります。
- 受給している年金の年額が18万円以上の方
- 介護保険料を年金から納めている方
- 後期高齢者医療保険料額と介護保険料額の合計額が、対象年金受給額の2分の1を超えない方
特別徴収対象者の保険料納付方法の変更
原則として特別徴収(年金からの天引き)となっていますが、申し出により特別徴収(年金からの天引き)を口座振替に変更することができます。
【申請方法】
- 事前に金融機関に「口座振替依頼書」を提出していただき、依頼書の本人控えとマイナンバーカードまたは資格確認書を持参のうえ、国保年金係または各支所地域振興課市民係へ申請してください。
- 申出人が本人もしくは同一世帯員でない場合は、委任状が必要です。
- 納めた保険料額は、国民健康保険税などと同じく所得税や住民税の申告の際に社会保険料控除の対象となります。
年金天引きでの納付:本人の社会保険料控除
口座振替での納付:口座名義人の社会保険料控除
申し出の期限はありませんが、申し出の時期により口座振替への変更時期が異なります。
普通徴収(納付書・口座振替)
納付書で納めていただく方
保険料の通知書に納付書が同封されています。納期限までに金融機関窓口等で納付してください。
令和7年度分の第10期(1月)、第11期(2月)、第12期(3月)の納付書は、令和8年1月にまとめて送付しています。
令和8年度分の納付書(第4期~第12期)は、令和8年7月にまとめて送付する予定です。
口座振替で納めていただく方
口座振替の手続きをしていただいた方は、納期限日に指定していただいた口座から保険料を引き落とします。
保険料の納付は口座振替がおすすめです
手続きは次の金融機関でできます。その際、口座の印鑑が必要です。
- 第四北越銀行
- 大光銀行
- 魚沼農業協同組合
- ゆうちょ銀行
- 新潟県労働金庫
- 新潟県信用組合
保険料の還付
保険料が納めすぎとなった方には、保険料還付の通知をお送りします。
後期高齢者医療制度に関する申請書
この記事に関するお問い合わせ先
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-757-3735
年金担当ダイヤル:025-757-3748
ファックス番号:025-752-6924
メールでのお問い合わせはこちら
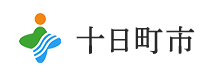
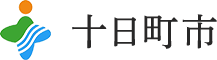
更新日:2025年10月01日