雪まつり・雪あそび
雪まつりのようすをおしえてください

十日町市は「現代雪まつり発祥(はっしょう)の地」と言われています。昭和25年に「雪を友とし、雪を楽しむ」という考えで、最初の十日町雪まつりがおこなわれました。
雪まつりには国内・外からたくさんの人たちがおとずれます。市内にはさまざまな雪像(せつぞう)や雪だるまができて、雪あそびが楽しめる「おまつりひろば」や、雪像コンテストなどさまざまなイベントがおこなわれます。(写真は昭和32年開催の雪上カーニバルの様子)
なぜ、雪まつりがはじまったのですか?

十日町雪まつりは昭和25年にはじまりました。それまで雪国の人たちは、スコップなどわずかな道具を使い、屋根の雪おろしや道路の雪かきをしていました。昔の人にとって、雪はたたかう相手だったのです。
そんななか、雪をうらめしく思い、暗く冬をすごすよりも「雪を友とし、雪を楽しむ」という考えで、雪まつりがはじまったのです。(写真は昭和47年から始まったコミュニティひろばの様子)
雪まつりでつくられる雪像(せつぞう)の大きさは、どれくらいですか?


雪像には、町内会や職場(しょくば)ごとにつくる巨大なものから、庭先につくる雪だるままで大きさはさまざまです。
約1週間〜10日くらいかけてつくります。大きさは家一軒くらいから、ダンプカーくらいまで、さまざまな大きさがあります。
雪の家(ほんやらどう)は、多ぜいの人が乗ってもこわれないのですか?


「ほんやらどう」は小正月の伝統行事(でんとうぎょうじ)として、1月14日の夜に近所の子どもたちがみんなで中に入って、ゲームをしたりごちそうを食べたりする雪の家です。上に乗るためのものではありません。がんじょうにできていますが、何人乗ったらこわれるかという実験をしたことがないので、答えはわかりません。
雪像(せつぞう)をつくっているときは、どんな気分ですか?


もちろん、みんなが芸術家(げいじゅつか)になった気分です。どうやったらすばらしい雪像ができるのかを考えながら、寒い中でもいっしょうけんめいがんばっています。なかには、雪像づくりが終わったあとのお風呂や、親睦会などを楽しみにしている人もいます。
雪まつりで使う雪は、とけないのですか?
真冬でも、天気がよくなると雪像(せつぞう)の表面がやわらかくなり、とけてしまうことがあります。ただし、雪まつりのあいだに雪像がぜんぶとけてしまうようなことはありません。



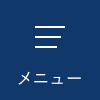
更新日:2021年08月24日