道路の工夫あれこれ
道路じょせつでは、機械のかつやくが目立ちます。しかし、それだけではありません。雪国には、よく見ないと気づかないようなところにも、雪からくらしを守るための工夫やせつびがたくさんあります。
道路のふん水「消雪(しょうせつ)パイプ」

消雪パイプは道路の上に地下水をまいて、雪をとかすしくみです。水温は10℃から14℃くらいなので、雪はとけてしまいます。道路の真ん中に、約1.5メートルごとに噴出口(ふんしゅつこう)が取り付けられていて、4方向に水が飛び出します。
消雪井戸(いど)は平均で150メートルくらいの深さがあります。90メートルくらいの深さに取り付けたポンプから、電気で水をくみあげます。ただし、地下水をくみ上げすぎると、地面が下がったり、地下水の不足がおこるので、水を使いすぎないようにしています。
市内には、平成30年10月現在、83.7キロメートルの消雪パイプがあります。
雪のウォータースライダー「流雪溝(りゅうせつこう)」

流雪溝は、水を利用して、雪を流す側溝(そっこう)のことです。流雪溝の中にはいきおいよく水が流されていて、スコップなどで投げ入れられた雪はあっという間に下流に消えていきます。投げ入れられた雪は、水といっしょに大きな川に流れ出し、さいごは十日町市の中央を流れる信濃川に合流します。
流雪溝を使うときにはいくつかのルールがあります。十日町市では、流雪溝の路線ごとに、水を流す時間を決めています。限られた水を効果的に使うための工夫です。それぞれの町内では時間割にそって雪を投げ入れます。上流(じょうりゅう)の町内と下流(かりゅう)の町内が自分勝手(かって)に雪を投げ入れると、大量の雪が流雪溝をふさぎ止めてしまうからです。
市内には、平成30年10月現在、51.2キロメートルの流雪溝があります。
雪がつもりにくい「たて型信号機」

雪国の信号機はたて型です。横型よりもたて型の方が、雪のつもる面積が小さくてすみます。信号機の上にたくさんの雪がつもると、雪が信号機のひさしから垂れ下がって、信号のライトをおおいかくしてしまうときがあります。信号が見えなくなって、交通事故がおきたら大変です。そこで、雪国の信号機は雪がつもりにくいたて型になっているのです。
信号機に雪がたくさんつもった時は、おまわりさんが雪を落とします。
雪の日もかさがいらない「アーケード」

アーケードの下では、歩行者は雪の日もかさをささずに安心して歩くことができます。しかし、アーケードの上につもった雪はときどき道路に落とさなくてはならないため、しばしば交通のじゃまになってきました。
そこで、平成6年からは市内にも融雪式(ゆうせつしき)のアーケードが登場しています。融雪式アーケードでは、雪はアーケードの上でとけるので、雪を落とす必要はなくなりました。
足もとも安心「融雪式(ゆうせつしき)歩道」

融雪式歩道は、ふった雪を地面の熱でとかす歩道です。融雪式歩道は商店街などでみられます。融雪式歩道の地面の下には、パイプがしきつめられていています。パイプの中を、ボイラーであたためられた不凍液(ふとうえき)〈凍(こお)らない液体(えきたい)〉が流れることによって、地面をあたためるしくみです。地面の雪や氷がとけるので、歩行者はすべってころぶ心配がなくなりました。
道路のすべり止め剤「塩化ナトリウム・塩化カルシウム」
気温が0℃以下になると道路がこおるため、塩化ナトリウムや塩化カルシウムをまき、こおらないようにします。
これらの薬には、こおる温度を下げる(凝固点降下という)はたらきがあるためです。



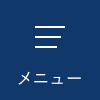
更新日:2021年04月26日