まちの中には工夫がいっぱい
なにげなく目にする風景の中にも、雪国の生活をかいてきに過ごすために工夫がたくさんあります。
三角屋根の電話ボックス

電話ボックスには三角形の屋根がついていて、雪がすべり落ちるようになっています。また電話ボックスは高さ約1メートルのコンクリート製(せい)の土台の上に乗っていて、入り口が雪でうもれにくくしてあります。
屋根のついたごみステーション

かわいらしいこのたて物、じつは町内のごみが集まるごみステーションです。とがった屋根で雪はすべり落ち、とびらによって雪が中にふきこむのをふせいでいます。
このように雪国のごみステーションは、各家庭から出されたごみが雪にうもれて放置(ほうち)されたり、カラスが生ゴミをつついたりするのをふせぐ工夫がしてあります。
消火栓(しょうかせん)の雪がこい


火事などのさいがいにそなえ、消火栓やぼうか水そうなどは、いつでも使えるように雪がこいをしておきます。
またひょうしきを立てておくことで、遠くからでも場所がすぐにわかるようにしてあります。
道路ぞいのポール

雪国の道路では、目立ちやすい色のポールが道路わきに10~20メートルくらいの間かくで立っているところがあります。
ポールを立てるのは、機械じょせつをする道路の境目(さかいめ)やとうげ道、側溝(そっこう)の開いているところなど、道路わきが危険な場所です。
機械じょせつでは、ポールを目印にして道路のはばをきちんとじょせつすることができます。
また、危険な所では運転手や歩行者にポールの外にはみ出ないように注意を呼びかけることができます。
雪のつきにくい「ヒレつき電線」
電線に雪がつくと、その重みで線がたるんだり、切れたりすることがあります。そこで、雪がつきにくい「ヒレつき電線」〈難着雪(なんちゃくせつ)電線〉が使われています。
川の中に川がある!?「低水路工(ていすいろこう)」

川の中心にもうひとつ水路がつくってあります。川を流れる水を、さらに水路に集めることによって、水をいきおいよく流すための工夫です。
これは「低水路工」という工事の方法です。川の水を水路に集めて「流雪溝(りゅうせつこう)」などから投げすてられた雪が、少しの水でもスムーズに下流に流れるようにしてあります
蛇口(じゃぐち)には保温材(ほおんざい)

冷え込みがきびしくなると、屋外の水道管や蛇口(じゃぐち)が凍って破裂(はれつ)することがあります。
こうした事故がおきないように、寒い夜には、凍りやすいところには発泡(はっぽう)スチロールなどの保温材をまきつけるようにしています。



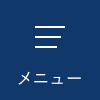
更新日:2021年04月22日