校しゃにも工夫がいっぱい
雪がすべり落ちる体育館

小学校の体育館などにも雪への工夫がしてあります。屋根のてっぺんには「雪わり」というとがった三角の形をしたものが付いていて、つもった雪が自然と両わきにすべり落ちるようになっています。
教室の上の体育館

山あいの小さな学校では、教室の上の階を体育館にしている校しゃがあります。たて物がたっている土地を節約(せつやく)して、雪かきなどの手間をはぶくことができます。
児童数(じどうすう)の多い学校では、必要とする教室の数が多いので、雪のふらない地方と同じように、教室のたて物と体育館は別々にたてられています。
雪の落下(らっか)を防ぐ「雪(せ)っぴ防止冊(ぼうしさく)」

「雪っぴ」とは、屋上などにつもった雪が、横にはみ出して落ちそうになっているかたまりのことです。
校しゃのわきや玄関(げんかん)の上から「雪っぴ」が落ちて、けが人がでないように、屋上には「雪っぴ防止柵」がとりつけてあります。「雪っぴ防止柵」は校しゃだけではなく、道路にめんしたたて物などにも取り付けられています。
屋外遊具(おくがいゆうぐ)のとりはずし
学校の校庭だけではなく、公園などの鉄棒(てつぼう)やブランコなど、屋外にある遊具は雪がふる前に取りはずします。そして、春になって雪が消えたら、ふたたび取りつけています。
なぜなら、雪の重みや雪消えのとき、雪が下に引っ張る力はとてもつよく、鉄棒が曲ったりブランコがちぎれたりするほどなのです。大雪の年には、大きな杉の木が幹(みき)から折れたりします。



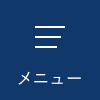
更新日:2021年04月22日