雪遊び・雪まつり
十日町雪まつり


十日町雪まつりは昭和25年にはじめて開催(かいさい)され、「現代雪まつり発祥(はっしょう)の地」と言われています。
昔の雪国の人たちは、冬になると屋根の雪おろしや、除雪(じょせつ)をしなくてはならず、大変な毎日をおくっていました。そのころは除雪をするにも大型機械がなく、人の力だけで雪とたたかわなくてはならなかったのです。
暗くしずみがちだった十日町の人たちが、「時には、雪との苦しいたたかいをわすれ、雪を友として楽しくすごそう」という思いから始めました。
今では毎年2月に開催され、国内・外からたくさんの人たちがおとずれます。市内には町内ごとに、市民の人たちがつくるさまざまな雪像が立ちならびます。あたたかいおもてなしや雪あそびが楽しめる「おまつりひろば」も各地でひらかれてにぎわいます。
雪国の楽しいスポーツ


雪国のスポーツでは、なんといってもスキーやスノーボードの人気があります。市街地(しがいち)から車で30分くらいのところに、スキー場があるのでみんなが手軽に冬のスポーツを楽しんでいます。
このほかにも、タイヤのチューブににた円形の輪(わ)に乗って、しゃめんをすべり降りるスノーチュービングという新しい遊びや、スノーモービルという雪上バイクを楽しむ人もいます。
十日町市やその周辺には、有名なスキー場がたくさんあって、毎年多くの若者や家族づれが、冬のスポーツを楽しみにやってきます。
昔ながらの雪遊び「しみわたり」


気温が下がり、雪がカチカチにかたくなることをこちらの方言で「しみる」といいます。
2月下旬(げじゅん)から3月ごろのよく晴れた朝には、雪原(せつげん)がかたくなって人が雪の上を歩けるようになります。そんなとき子どもたちは雪原にでかけてあそびます。
かたくなった雪の上を歩くことを「しみわたり」といいます。どこまでも続く真っ白な雪原を歩くのはとても楽しいですよ。リスや野うさぎの足あとを見ることもあります。
鳥追(とりお)い、ホンヤラドウ


毎年1月14日の夜から15日の早朝にかけて、鳥追い行事が行われます。
鳥追い行事では、それぞれの町内ごとにホンヤラドウとよばれる雪の家がつくられます。ホンヤラドウは、おわんをひっくり返し、中をくりぬいたような形のものや、積(つ)み上げた雪かべで四角い部屋をつくり、シートや木の板で天井をはったものがあります。
14日の夜、子どもたちはストーブやこたつを中に持ち込んで、暖(だん)をとり、ごちそうを食べながら、夜ふけまで遊びます。ころあいをみて、隊列(たいれつ)を組み、拍子木(ひょうしぎ)を打ちならしながら、「鳥追い歌」を歌って町内をまわりました。
「鳥追い歌」の歌詞(かし)は、しゅうかくの季節に作物を食べあらす害鳥を追い払い、豊作を願う内容です。
昔は、畑や田んぼでとれる作物のしゅうかく量も今より少なかったので、鳥に作物を食べられるというのは、大きな心配ごとだったのです。昔にくらべ、「鳥追い歌」はあまり歌われなくなりました。しかし、ホンヤラドウだけは今でも子どもたちの冬の楽しみとしてさかんに行われています。
炎の行事 バイトウ


大白倉の小正月行事バイトウ。
雪とケヤキとわらで作った一夜限りの家の中央には、ジロ(いろり)が設けられ、火の回りに老若男女が集います。宴もたけなわになった夜半、全員で「天神ばやし」を斉唱。最後に家に火をつけて新春を祝い豊作を祈る、豪快な炎の行事です。
むこなげ、すみ塗り


毎年1月15日、松之山温泉で小正月行事のむこ投げとすみ塗りが行われます。
約300年の歴史があると言われているむこ投げは、ムラの娘をよそへ嫁に取られた腹いせから始まったと言われています。前の年に結婚したむこは、威勢のいい若い衆に肩車され坂の上の薬師堂まで担ぎあげられます。そこから約5メートルのがけ下へ投げ出されると、観客から大歓声と祝福の声があがります。
むこなげが終わるとすみ塗りの始まり。正月に飾られた門松やしめ飾りなどをわらで組み上げ、おごそかに火を入れます。この、さいの神が下火になると、灰を手にとって「おめでとう」を言いながら、だれ彼なく顔にすみを塗りあい、今年1年の無病息災と家業の繁栄を祈ります。



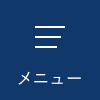
更新日:2021年04月22日